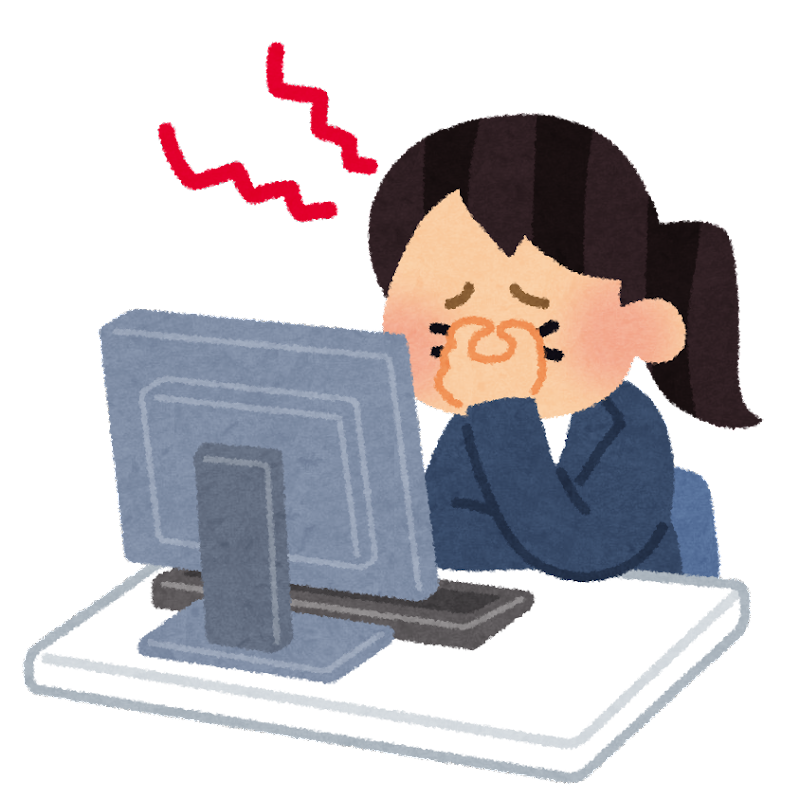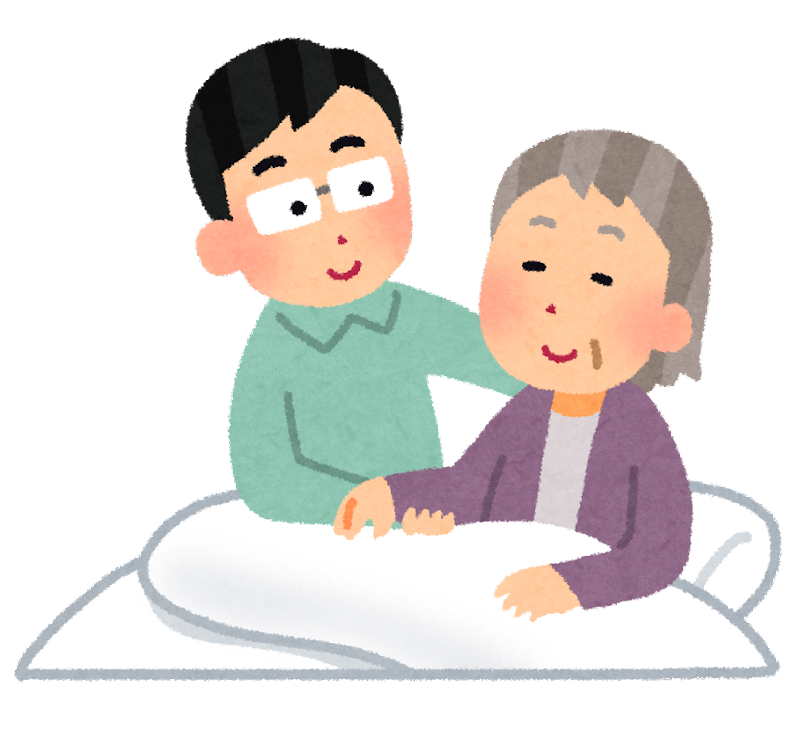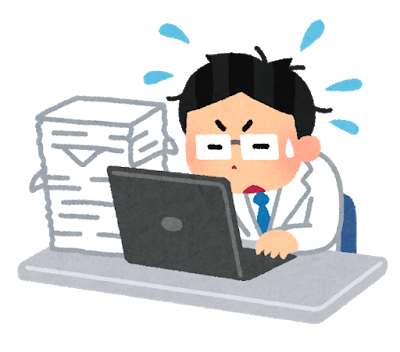皆様の職場には何人くらい新入社員が入社されましたか?元気に頑張っていらっしゃるでしょうか?
産労総合研究所では今年の新入社員は、「自分の未来は自分で築く!「セレクト上手な新NISAタイプ」」と発表されていました。また、厚労省では、新規学卒就職者の離職状況として、就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者 37.0%、新規大卒就職者 32.3%でした。 どの企業も新人獲得とともに定着は課題になっています。
先日4月に研修をさせて頂いた新人の方と個別面談をさせて頂く機会がありました。研修時は朝食を食べていなかったのですが、先日の面談時に伺ったら朝食を食べるようになっていました。詳しく変化を聞いたところ、朝食をなぜ食べた方がいいのかがわかり、簡単な方法もいくつか知ったのですぐにやってみましたとのことでした。そして、実際にやってみたら体の調子がとてもよく、朝も起きられるようになったと笑顔で話されていました。
私は、なぜそれをするのかの目的もしっかり伝えて、いかに具体的にアドバイスをお伝えするかはとても大切だと思っています。また、どんなに小さなことでも実践してみたことは思いっきりほめるようにしています。これにより自己効力感も高まりさらに行動してくれますし、何より自信がつきます。そして、面談の最初や日頃から「最近どうですか?何か気になっていることはありますか?」と聴いたり、面談の最後には「ここまでで何か質問はありますか?言い足りなかったことはありますか?」と理解度等を確認したり、「いつでも話しに来てくださいね」と相談できる先があることを必ずお伝えしています。
大切な新入社員の方が元気にしっかり配属先で頑張って頂けるように本人は勿論ですが、受け入れる職場のメンバーの方との信頼関係を作るためにも、日頃からの丁寧なコミュニケーションの積み重ねが大切だと思っています。